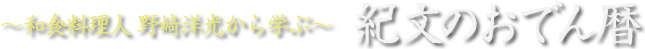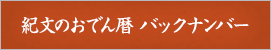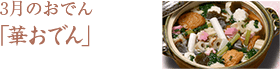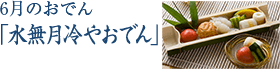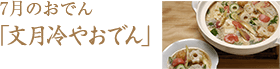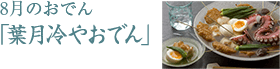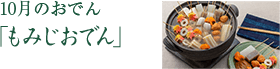今月は、深まる秋の香りを楽しむ「きのこ」を使ったおでんです。食物繊維が多く含まれているきのこは、素朴ながらも旨味が充分に含まれる素材。ふっくらとしたはんぺんとあわせることで、きのこの食感を愉しむことができます。古くは「身土不二」、最近では「地産地消」という言葉もあるように、昔から地域で採れた食材を食べると、身体に良いとされています。地元の新鮮な素材をたっぷり使い、地域ごとの味わいをおでんにも取り入れてみましょう。
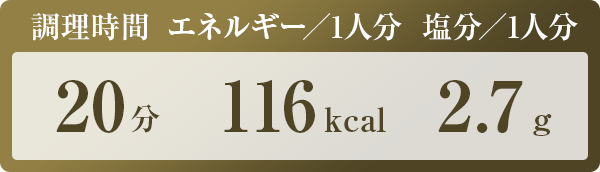
今月の旬の素材きのこ
旨味成分がたっぷりのきのこは、よいだしが出るので、おでんに適した食材です。歯ごたえや風味を生かすため、火を通しすぎないよう手早く調理しましょう。
えのきだけやしめじは、石づきにハリがあり、みずみずしいものを選ぶようにしましょう。

材料(4人分)
| さつま揚 | 1パック |
| はんぺん(大判) | 1パック |
| マリーン®(カニカマ) | 12本 |
| しいたけ | 4個 |
| しめじ | 1パック |
| えのきだけ | 1パック |
| なめこ | 1パック |
| みつば | 1/2束 |
| ゆず(皮を千切り) | 適宜 |
| (A) | |
| 水 | 1000ml |
| 薄口しょうゆ | 40ml |
| 酒 | 20ml |
| 昆布 | 10×10cm |
作り方
- 1:しいたけは軸を取り除く。しめじは石づきを取り、房ごとに小分けにする。えのきだけは石づきを取りほぐす。
- 2:はんぺんは、カニカマの大きさに切る。
- 3:みつばはさっとゆで、食べやすい大きさに切る。
- 4:鍋にお湯を沸かし、きのこ類、さつま揚を入れて30秒したらざるに取り、汁けをきる。(この行程を霜降※りという)
- 5:鍋にAときのこ類、さつま揚を入れ、火にかける。沸騰したら、はんぺん、カニカマ、みつばとゆずの皮を入れる。
- 6:<霜降り>魚介類や肉などの下処理方法。表面が白くなる程度に熱湯を通したり、かけることにより、素材のくさみやぬめりを取り除くことができます。

しいたけの軸を切る(作り方1参照)。しいたけの汚れが気になる時は洗わずにペーパータオルでそっとふきましょう。
※霜降り:魚介類や肉などの下処理方法。表面が白くなる程度に熱湯に通したり、かけることにより、素材のくさみやぬめりを取り除くことができます。
 野﨑流和料理のこころ
野﨑流和料理のこころ
〜「身土不二」という考え方日本の食文化を再考する〜
-
壱、きのこも「霜降り」をすれば、すっきりとした味わいに
うま味成分のあるきのこは、良いだしが出る食材の一つです。栽培されたきのこが多く流通している現代は、一年中きのこを食べることができますが、この季節には、ぜひ天然のきのこも取り入れてみましょう。天然のきのこの場合、長時間煮ても旨味が残り、味は変わらないのですが、栽培されたきのこには、きのこ特有の雑味があります。表面の汚れなどを取るためにも、きのこを調理前に熱湯にくぐらせる「霜降り」をすることで、独特の臭みやアクが抜け、すっきりとした仕あがりになります。
-
弐、煮すぎないおでん。温め直しは電子レンジで
作りたてのおでんを食べることができるのは、家庭ならでは。ぜひ美味しい状態のうちに食べてください。おでんを温め直す場合は、煮返す必要のない電子レンジを使いましょう。煮返す度に崩れたり汁の味ばかりになる心配もなく、素材そのものの味を楽しむことができます。
-
参、地産地消。地元の食材をいかして、おでんの具材も無限に広がる
「地産地消」という言葉が示すとおり、それぞれの家庭が地元でとれた新鮮な食材を使えば、美味しい料理が生まれます。おでんも同様で、素材の旨味を引き出し、素材の味を際立たせれば、素朴ながらも滋味深いおでんができます。旬の食材、そして地元にある身近な食材を使い、ご家庭ならではのおでんを楽しんでください。